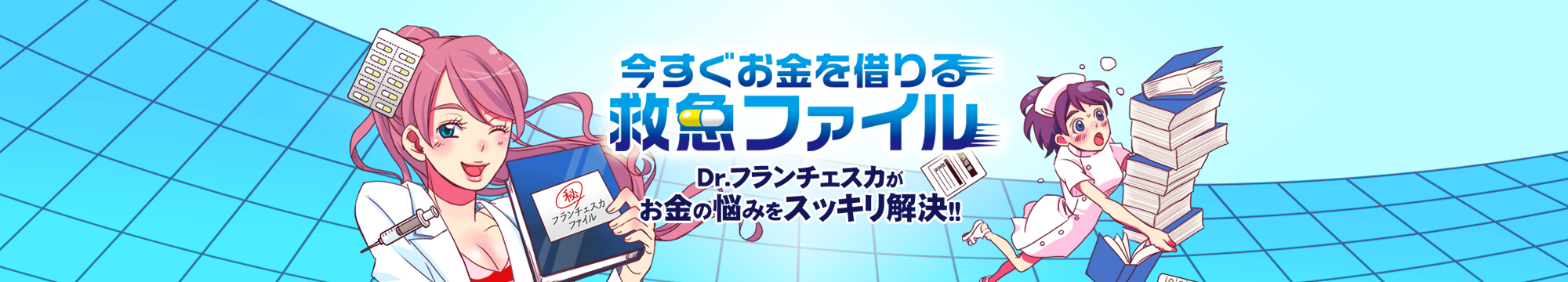生活が苦しく、固定資産税を支払えないでいると、そのうち督促状が届くことになります。
しかし、生活すらままならない状態で、到底固定資産税など払えないという場合にはどうしたらよいのでしょうか。
今回は生活がぎりぎりで固定資産税滞納に対して督促状が来ているけれど払えない、そんな人のための解決策や督促放置のリスクを解説します。
固定資産税が払えないとどうなる?
まずは固定資産税が支払えなかった場合の督促、そしてやがて差押えが来る前のカウントダウンがどのようにされるのかについて見ていってみましょう。
督促状を支払いができないからといって無視し続けると、その後差し押さえ通知が届くまでの期間や時系列、どこまで行くと実際に差し押さえられてしまうのかなどの流れをご覧ください。
督促から差し押さえまでの期間と流れ
実際に固定資産税を滞納した場合、どれくらいの時期にどういった通知や警告が来るのかについて、一連の流れを見ていってみましょう。
固定資産税を滞納し始めてから、まず最初の督促状が届くことになります。
納付期限から20日以内に督促状の発送
固定資産税の納付期限から20日が過ぎる頃になると、延滞しているから支払いをするように促す督促状が届きます。
通常督促状の発送は地方税法371条によって定められていて、20日以内に督促状がハガキで送付されることが多いでしょう。
督促状に記載されている内容は、延滞金が生じている、さらに差し押さえといったペナルティが課せられる可能性があるという事が記載されています。
この督促状を皮切りに、それぞれの期日で、滞納者にはさまざまな手段や対策が講じられることになります。
10日以内に完納できない場合は差し押さえが可能に!?
督促状を受け取ってから10日以内に滞納している固定資産税を完納できない場合、市役所や区役所といった行政機関は差し押さえをする権利を持つことになります。
しかし10日過ぎたからある日突然差し押さえをするのではなく、電話によってさらに督促する、督促状を再度送付するなどの対処になることがほとんどです。
督促を無視し続けると財産調査や身辺調査がスタート
督促を無視し続けると、行政機関は滞納者に本当に滞納する理由があるのか、お金があるのに税金の支払いを拒否しているのではないかという財産調査を開始することになります。
同時に、お金の使い方や資産差し押さえなどに向けて、身辺調査もスタートするでしょう。
金銭的余裕があるかないか、無駄使いや浪費によって税金の支払いが滞ってはいないかなどについて調査します。
差し押さえ容易な給与口座が狙われる!
固定資産税の督促状を無視、再三再四にわたる勧告にも応じない場合、差押えが容易な給与口座から差し押さえられることになるでしょう。
その他預貯金や持ち物についてもどんどん差し押さえられていくことになります。
財産の売却「物納」で滞納金に補填!どんな財産が差し押さえ対象?
差し押さえられた財産は売却されるなどして、滞納金に補填されることになります。しかし全ても持ち物が差し押さえの対象物となるわけではありません。
財産差し押さえの対象となるもの、さらに差押禁止財産にはどのようなものがあるのでしょうか。
差押えの対象となる財産
- 不動産
- 有価証券
- 車
- 宝石
- ゴルフ会員権
- 電話加入権
- 給与
- 年金
- 退職金
- 敷金
差押え禁止財産となるもの
- 家財道具
- ペット
- 衣類
- 3ヶ月分の食料や燃料
- 生活保護費
- 児童手当
- 仕事に最低限必要な道具など
滞納期間に延滞金が発生
固定資産税を期限までに支払わなかった場合、延滞税という税金も発生します。
本来の納期限後、約1ヶ月以内であれば年2.9%、1ヶ月を超えてしまうと年率9.2%の延滞金がかかることになります。
元本の支払いが終わらなければ、永遠に本税にプラスして延滞金が加わってしまうことになります。
ただし延滞金については、特例基準割合というものがあり、特例の割合が本則を超える場合には本則の利率が加算されます。
特例基準割合は毎年変動するため、一概に加算される額がどうなるかという事は言えません。
固定資産税が払えない場合は素早く相談!差し押さえ回避の対処法
生活が苦しく、固定資産税の支払いが難しいという場合には、どのように対処することが望ましいのでしょうか。
対処の仕方によっては差し押さえを回避することもできますし、一度に大金を支払う必要がない場合もあります。
ここからは相談先や相談内容などについても解説していきます。
滞納した固定資産税の3つの分納方法
滞納した固定資産税は、窓口や担当者、担当部署に相談することで以下のような分納方法によって支払い方法を変えることができます。
一度に負担する額が小さくて済むため、経済的負担も軽減されますが、それぞれメリットデメリットがあるのも事実です。
どの方法が自分にふさわしいか、しっかりと利用条件や特徴、長所と短所を見極めて利用するようにしましょう。
通常分納
通常分納という方法は、滞納していた分の固定資産税を分割扱いにしてもらって支払う方法です。
各役所の徴収担当者に口頭で相談することによって、後日分割払いのための納付書が届き、その用紙で支払いができます。
通常分納は最も簡単にできる手続きですし、滞納してばかりいる悪質な滞納者でない限り、電話のみで対処してくれるという場合もあります。
しかし分納にしてしまったにもかかわらず、期日までに支払いができなかったという場合には、弁明の機会を与えられずに言い訳することもできません。即差し押さえの手続きをされるなどのリスクがあります。
固定資産税の相談をしたいけれど行く暇がない、まとまったお金を支払うことができないという場合で、今まで滞納ばかりしているという事実がない人は、まず電話で相談してみるようにしましょう。
【通常分納のメリット】
- 手続きが簡単ですぐにできる
- 分割で支払うことができ経済的負担が軽減される
【通常分納のデメリット】
- 延滞税についての免除は無し
- 弁明の機会が一切ない
- 差押えのリスクを避けられない
納税の猶予
延滞税についても支払うことが難しい場合には、納税の猶予という方法もあります。
納税の猶予を適用されるためには、一定の条件をクリアしている必要があります。
誰でも利用できるという方法ではありませんが、本当に困っている人にとってはかなり有効な方法だといえるでしょう。
- 災害や盗難にあってしまった
- 本人や家族がケガや病気をしている
- 事業などで著しい損害を受けてしまった
- 事業が停止または廃止してしまった
- 災害、盗難、ケガや病気に類似するような事柄が起こってしまった
- 事業の休止や廃止、停止などに類似するような事柄が起こってしまった
上記の6つの条件のうち、1~4に該当する人は、延滞税が100%全額免除されることになります。
また、払えない理由が5、6という人については、延滞税を50%免除してもらうことができます。
そして納税の猶予が認められた場合、滞納していたとしても支払わなかったからといってすぐに差し押さえになるということもありません。
納税の猶予については以下のような流れに沿って適用されますが、支払わなかった理由に正当性がある場合には、弁明の機会が与えられますし、言い訳が納得できるものであれば差し押さえも待ってもらうことができます。
【納税の猶予の申込みの流れ】
- 徴収猶予申請書と必要書類を提出する
- 現在納不可能資金額(今払えるだけのお金)の振り込みをする
- 行政による書類調査を受ける
書類審査に合格すると、分割払いによって固定資産税の支払いがスタートします。納期に遅れないように支払うことで、経済的負担を軽減しながら納付していくことができます。
【納税猶予のメリット】
分割で支払うことができる
延滞税の免除が受けられる
【納税猶予のデメリット】
手続きが非常に面倒
換価の猶予
差押えの解除や、残りの税金を分割払いにしてもらうことができる、さらには延滞金の50%免除もあるという方法が換価の猶予です。
換価の猶予が認められると、差し押さえのリスクを回避することができます。しかし利用できる条件は非常に厳しく、以下のような条件を完璧に満たしている必要があります。
条件に適合し、さらに誠実にこの先税金を納めていくという態度を示したとしても相当難しい方法になります。
【換価の猶予の条件】
- 差し押さえられてしまった財産を処分されると、生活や事情に支障が出る
- 固定資産税以外の税金の滞納が全く無い
- 納税するという誠実な意思や気持ちが認められる
【換価の猶予のメリット】
差押さえを解除することができる
最長2年の分割払いが可能になる
延滞税の50%免除
【換価の猶予のデメリット】
手続きが面倒
窓口でもなかなか認められない
各自治体の窓口によってかなり対応が異なる
そもそも税金の督促を無視して差し押さえられた時点で不誠実だと判断される
滞納処分の停止制度は条件が非常に厳しい
実は滞納分の固定資産税をゼロにする方法もないわけではありません。この方法は、滞納処分の停止制度という方法になりますが、条件は非常に厳しいといえます。
最大のメリットとしては、やはり今まで滞納していた分の固定資産税の支払い義務がなくなるという点です。
一般の個人に対しても、個人事業者に対しても適用される制度で、国税徴収法153条に掲載されています。
行政による調査や審査に通過すると、滞納処分の停止通知書が届き、3年が経過した時点で滞納していた税金の納税義務が完全に消滅します。
適用条件としては、以下のような条件を満たす必要があります。
- 差し押さえる財産を売却しても滞納分の回収が見込めない
- 滞納処分によって生活できなくなる恐れが生じる
- 滞納者の居場所(住所)や財産が不明
相続不動産の固定資産税が払えないときの解決法はある?
基本的に相続不動産の固定資産税は、相続人に支払い義務があるといえます。
例えば親が亡くなって相続した土地や、空き家になっている実家などについても固定資産税が発生し、相続人に請求が来るということになります。
ここで相続した不動産の固定資産税を滞納してしまうと、その場所の財産だけでなく、現住居の差し押さえという事にもなってしまいます。
相続人は支払うべき税金の納税者ということになっていますから、滞納すれば当然相続人の財産や不動産、資産などが差し押さえられることになるのです。
差し押さえの流れとしては、一般的な督促や差押えの流れと一緒で、20日以内に督促状が発送され、さらに督促状から10日以内に支払わなかった場合には差し押さえの対象となります。
住宅ローン返済中に固定資産税が払えないときの解決策はある?
住宅ローンの返済中に、生活資金繰りが苦しくなり固定資産税が払えなくなってしまった場合には、住宅ローンの借り換えも検討すべきだといえます。
借りに差し押さえになってしまったとしても、住宅ローンについては支払っていかなければなりません。
ローン残高がどれくらいあるのかをしっかりと把握し、複数の金融機関に借り換えローンの打診をしてみるなどの対策が必要でしょう。
住宅ローンの借換えをしてみても、まだ生活状況が改善しない、固定資産税の支払いが難しいという場合には、マイホームの任意売却も検討したほうが良いでしょう。
早期に任意売却することで、ある程度の生活資金を手元に残しながら固定資産税の滞納分を支払うこともできます。また売却資金をローン返済に充てることもでき、資金繰りが一気に良くなることが多いものです。
固定資産税が払えなくても自己破産はダメ?!
生活が苦しく資金が乏しいからといって、むやみに自己破産をするのはおすすめできません。安易な自己破産は、さらに自分の生活を困窮させてしまう可能性も秘めています。
また自己破産したとしても、固定資産税の支払い義務が免除されることは原則ありません。
固定資産税などの税金の支払いが大変だからといって、安易な考えて自己破産してしまっては後々大きな後悔が待っていることになるでしょう。
老後破綻!?年金受給者が固定資産税を払えない!?
平均寿命が長くなってくるのと同時に問題となっているのが、老後破綻と課題です。
年金受給者になっても、固定資産税の支払い義務が解除されるということはなく、資産を保持している人には固定資産税の支払い義務があります。
終の棲家が老後破綻の原因を作り出してしまうというケースも少なくありません。
年金受給者になって老後を平穏に暮らしたいと考えている人は、年金受給者になっても固定資産税の支払いが継続するという事をしっかりと理解しておく必要があります。
行政による取り立ては貸金業者より厳しい!?
納税は国民の義務であり、全国民が税金を平等に納める必要があります。
そのため、行政による固定資産税という税金の取り立ては、貸金業者並み、またはそれ以上に厳しい場合も時にはあります。
数千円の固定資産税を徴収するために、他県をまたいで徴収に行くという事も少なくなく、支払いが完了するまで追われ続けることになるでしょう。
そのため税金逃れのために移転したり、逃げ隠れしたとしても、滞納の支払いをずっと迫られるということもあります。
固定資産税の滞納を解消するためには、しっかりと窓口や担当部署、徴収員に相談して、何とか納税することができるように、誠実な態度や姿勢で臨む事が大切です。
支払い義務を全うしようという真摯な姿勢を見せることで、分割納付や猶予期間を設けるなどの措置も受けやすくなります。
まとめ
固定資産税の支払いが難しい経済状況の時には、その事を正直に担当者に話し、何とか滞納を解消し、納税することができるような方法を一緒に考えてもらうのが得策です。
一度滞納してしまうと滞納癖がついてしまい、その後も滞納を繰り返すようにもなってしまいます。そうなるとさらに滞納額が膨らみ、本来であれば払う必要のない延滞金まで加算され、余計支払いが難しくなっていくでしょう。
そうなる前に督促から逃げず、真摯で誠実な姿勢で完納を目指すようにしましょう。