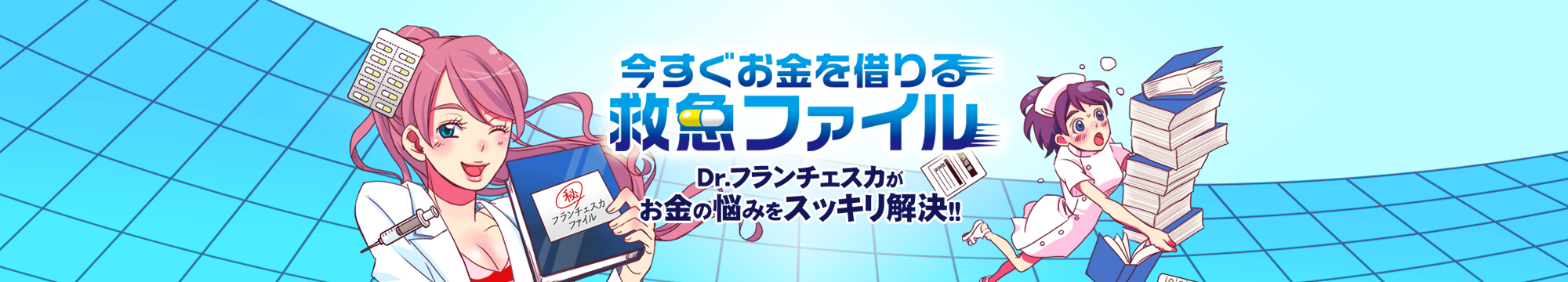「親を扶養に入れると税金が安くなる」という話は良く知られていますが、親を扶養に入れるとメリットが多いことは確かに本当のことです。
しかしメリットばかりでなくデメリットがあるという、もう一つの側面についても理解しておく必要があるでしょう。
今回は親を扶養に入れるのと入れないのとでは、どういった違いがあるのか、自分だけでなく親側のデメリットはあるのかという点について考えてみましょう。
親を扶養に入れるかどうか迷っている、親を扶養に入れることでどれくらいのメリットが得られ、どのようなデメリットが生じるのかを知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
親を扶養に入れるメリットってなに?
まずは親を扶養に入れることで得られるメリットについて見ていきましょう。
扶養には税金上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。この2種類の扶養は全くの別物、条件や手続きもまるっきり異なるといえます。
親を扶養に入れることで得られる税金上のメリット、さらに社会保険上のメリットとはいったいどのようなものなのでしょうか。
子どもの側では税金が安くなる
実は税金上の扶養に関して言えば、税金上ではメリットしかないということができるでしょう。もし扶養の条件に該当するのであれば、扶養に入れる方が得策です。
親を税金上の扶養に入れることで、扶養控除として自分の所得から差し引いてもらうことができます。これによって所得税と住民税がかなり安くなります。
親の側では国民健康保険等の保険料が不要になる
社会保険上の扶養でのメリットは、基本的に親の国民健康保険料が無料になるということです。
親の負担を減らすことができる上、自分自身の社会保険料が高くなるということもありません。
親を扶養に入れると、どのくらい節税できるの?
では親を扶養に入れた場合、どれくらいの金額を節税できるのでしょうか。
ここからは所得税、住民税などがいくらくらい節約できるのかについて解説します。
親を扶養に入れて節税する場合の注意点としては、扶養に入れる親、つまり老人扶養親族の年齢によって控除金額や税金が変わるという事です。
自分の親を自分の扶養に入れると、以下の金額が所得から配偶者控除などと同様に控除されることになります。
| 親の状況 | 控除金額 |
|---|---|
| 親が70歳未満 | 38万円 |
| 親が70歳以上で別居 | 48万円 |
| 親が70歳以上で同居 | 58万円 |
| 親の状況 | 控除金額 |
|---|---|
| 親が70歳未満 | 33万円 |
| 親が70歳以上で別居 | 38万円 |
| 親が70歳以上で同居 | 45万円 |
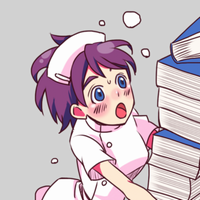 あすか
あすか納税者又はその配偶者と常に同居している人を同居老親と呼びます。
扶養に入れる条件ってあるの?
親を扶養に入れることには多くのメリットがありますが、実際に親を扶養に入れる際の条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
親を扶養に入れるには、以下のような条件を満たす必要があります。
条件をクリアしていればかなり節税になるので、親を自分の扶養に入れる手続きをしましょう。
税金面で扶養に親を入れる場合
税金面で親を扶養に入れる場合には、以下の2つの条件をクリアしている必要があります。
- 親の年間の合計所得が38万円以下
- 親と子が生計を一つにしている
以上の条件を満たしていれば、親を扶養に入れることができます。
実際に生計が一緒ではなく別居していたとしても、生活費や医療費などを仕送りしているという実態があれば、別居であっても生計が同一とみなされ条件適用となります。
また税金面での扶養は、配偶者の親でも同別居に関わらず対象となるのでメリットが大きいといえます。
障害年金しか収入がない場合、税法上、障害年金は非課税なので必ず税法上の扶養に入れます。また、障害年金受給者が家族の扶養に入ることで生じるデメリットはありません。
健康保険上の扶養に親を入れる場合
健康保険上の扶養に親を入れる場合には、以下の3つの条件をクリアする必要があります。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者であれば180万円未満)
- 別居親の収入が被保険者(子)からの仕送り額未満
- 同居親の収入が被保険者(子)の収入の半分未満
以上の3つの条件を満たしていれば、健康保険上の扶養に親を入れることができます。
親を扶養に入れる手続きってどうするの?
条件をクリアし、親を扶養に入れる場合の手続きについても詳しく解説します。
手続きを行うことで、払う税金が少なくて済むだけでなく、親の負担を軽減してあげることができます。
親を税金上の扶養にする手続き方法
親を税金上の扶養に入れるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入の上、年末調整の時期に会社に提出するだけでOKです。
申告書は会社の経理からもらうことができます。会社側は提出された申告書に基づいて、源泉徴収をしていきます。
年末に手続きをする理由は、税法上の理由からです。税法上、12月31日の年末の状態によって納税額の計算をしますので、年内に処理されているという必要が出てきます。
今年からすぐに税金を減らすことを考えると、年内に書類を提出して年末調整で処理してもらうという事が大切なのです。
給与所得者が会社に扶養控除等(異動)申告書を提出するときには、扶養に入れる親の収入の状況がわかる課税証明書や非課税証明書、源泉徴収票なども一緒に提出します。
提出書類や必要書類は会社によって異なるため、どのような書類が必要か担当者や経理に確認しておきましょう。
親を健康保険上の扶養にする手続き方法
健康保険上の扶養に親を入れる場合の手続きに関しては、親と同居しているか別居しているかで手続きが異なります。
基本的には税法上の扶養と同じように、会社に「健康保険被扶養者(異動)届」という書類を提出することになりますが、ほかにも準備する書類があります。
同居している親の場合
同居している親を扶養に入れる場合には、以下の書類を揃えて提出します。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 世帯全員の住民票 | 被保険者の戸籍謄本(戸籍抄本)/被保険者との続柄がわかるもの |
| 親の課税(非課税)証明書 | 年収によっては条件をクリアできない場合があるため |
別居している親の場合
別居している親の場合には、自分と続柄がわかるものや、生活のためのお金を仕送りしていることがわかる書類、生計を支えているということが証明できるものが必要となります。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 親の戸籍謄本 | 扶養に入れる親と自分の関係性、続柄がわかるようなもの |
| 仕送りを証明するもの | 仕送り額や仕送りの事実がわかるもの、振り込みの場合には預金通帳等の写し、送金の場合には現金書留の控えなど |
親を扶養に入れるならどのタイミングがいい?
親を扶養に入れるベストなタイミングとしては、親が退職して年金収入のみとなった時や、年末調整で12月31日の時点の扶養状況で判断が下されるという事を考慮し年末12月が良いでしょう。
将来的に介護の可能性も考慮して、同居を検討する人も多くいます。
同居の場合は、親を扶養に入れやすくなるので合わせて検討してみてもいいかもしれません。
親を扶養に入れるタイミングが12月だと、初年度だけですが、実質1ヶ月分の扶養で1年分の節税効果が見込めます。
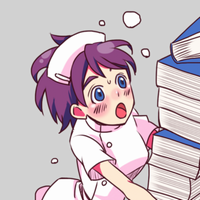 あすか
あすかここまでタイミングよく扶養に入れることは難しいかもしれませんが、もし可能であれば12月を狙ってみましょう♪
親を扶養に入れたときのデメリット
実は親を扶養に入れるときに、気を付けるべきデメリットがあるのも事実です。
ここからは親を扶養に入れたときに生じるデメリットや注意点について詳しく解説していきます。
75歳以上の親には効果が少ない
親を扶養に入れたいのであれば、まだ親が若く健康的な時期がおすすめです。理由としては、親が75歳以上の高齢になると、健康保険上の扶養に入れることができないからです。
75歳以上の年齢になると、医療保険の面は後期高齢者医療制度に移行してしまいます。
税金上の扶養に入れることはできますが、社会保険上の扶養についていえば、親の健康保険料や医療費控除などは全く効果がなくなるデメリットがあります。
75歳未満でも医療費の自己負担が増加する可能性がある
75歳未満は健康保険上の扶養に入れることはできませんが、親が75歳未満であっても高額医療を受けていたり、月々に一定以上の通院費、薬代がかかっている親の場合には、自己負担が増加してしまう可能性があります。
こういった親の場合は、医療費自己負担の増加分が節税額を上回ってしまうこともしばしばで、扶養に入れることで医療費負担が増加してしまうのがデメリットといえるでしょう。
定年退職後の収入は年金が中心になることもあり、高額療養費の自己負担限度額も70歳以上の人は現役世代よりも低く設定されています。
ただし実の親の場合は、世帯分離して扶養に入れることも可能です。配偶者の親の場合には同居が要件になるので注意が必要です。
親が65歳以上になると、親の介護保険料は年金から天引き
また注意点として、親が65歳以上になると、親の介護保険料は親の年金から天引きになります。
親を健康保険上の扶養に入れたとしても、この介護保険料分が無料になる事はありません。
親を扶養に入れるときの税制上の注意点
親を扶養に入れる手続きは意外と簡単で、親を扶養に入れることでさまざまなメリットが得られますが、実は税制上で親を扶養に入れる前に確認してきたいポイントがあります。
他の兄弟も仕送りしている場合
当然のことながら、扶養は誰か一人の人にしか入ることができません。他の兄弟も親に仕送りをしている場合には注意が必要だといえるでしょう。
既にほかのだれか兄弟の扶養に入ってしまっている場合には、当然ほかの人の扶養に入れることはできません。
親や兄弟など親族に自営業の方がいる場合
自営業の親族がいる場合にもしっかりと確認しておきたい点があります。
自営業を営んでいる親族の専従者として申告している場合、その親は扶養に入れることができなくなります。
親や兄弟、親族に自営業の人がいる場合には十分に確認が必要です。
親を扶養に入れる前にメリット・デメリットを比較する
ここまで親を扶養に入れる前に知っておきたいメリットデメリットをご紹介しましたが、親を扶養に入れるかどうかは、入れる前と入れた後で節約できる額がどれくらいなのかを十分に比較検討しておく事が大切だといえるでしょう。
親にとってみれば、健康保険料をタダにできたうえ、子供からの仕送りや生活のための資金を得ることができますし、子供側からしてみると大幅に節税することができるというメリットがあります。
しかしケースによっては親の所得区分が変化して医療費増大というリスクを背負う可能性もあります。
こうしたデメリットの側面も十分に理解したうえで、扶養に入れるかどうかの検討が必要です。
まとめ
親を扶養に入れれば節税できてラッキーだしメリットばかり、そう考えていた人にとっては目から鱗だったのではないでしょうか。
税制上や社会保険上の扶養メリットの反面、注意すべき点や隠れたデメリットがあるという事を知っておくことが重要なのです。
自分や親の負担がどうなるのか、安易に親を扶養に入れるまえにデメリットもしっかり検討してみましょう。